競争と協力、どちらも大切なチームの要素
ビジネスの世界では「競争」と「協力」、一見相反するこの2つの要素をどうバランスよく取り入れるかが大きな課題になっています。皆さんのチームではどうでしょうか? 部下同士が競い合っていますか? それとも協力し合っていますか?
良い競争が生み出す成果とモチベーション
適度な競争は個人の成長を促す強力な原動力になります。例えば営業部門での売上ランキングや、プロジェクトでのアイデア出しコンペなど、明確な目標に向かって切磋琢磨することで、メンバー一人ひとりのスキルや知識が向上していくのです。
2021年に行われたデロイトの調査では、適切な競争環境を取り入れている企業では従業員のエンゲージメントが平均23%高いという結果が出ています。また、Google社の「20%ルール」(業務時間の20%を自由なプロジェクトに使える制度)では、社内で良い意味での競争が生まれ、Gmail、Google Newsなどの革新的サービスが誕生しました。
ただし、競争が行き過ぎると問題が発生します。短期的な成果だけを追求するあまり、長期的な視点が失われたり、同僚を敵と見なして情報共有が滞ったりすることも。これではチーム全体のパフォーマンスが低下してしまいます。皆さんのチームでも、競争が激しすぎて疲弊している様子はありませんか?
協力がチームを強くする理由
一方で、協力体制もチームの成功には欠かせません。異なる専門性や視点を持つメンバーが協力することで、個人では思いつかなかったアイデアが生まれたり、複雑な課題も分担して効率的に解決できたりします。
エドモンドソン教授の研究による「心理的安全性」の概念は、協力の重要性を示す好例です。失敗を恐れず意見を言い合える環境では、イノベーションが生まれやすく、問題解決も迅速になります。実際、Microsoftの研究部門では、異なる専門チーム間の協力を促進するため「One Microsoft」という取り組みを実施。部門間の壁を取り払った結果、クラウドサービスの開発スピードが1.5倍に向上したという事例があります。
皆さんは日頃、チームメンバーと十分に協力できていますか? 各自の専門性や強みを活かし合える環境になっているでしょうか?

バランスの取れたチームビルディング手法
競争と協力、どちらも大切なこの要素をバランスよく取り入れるための具体的な方法を見ていきましょう。
競争と協力を両立させるゲーム形式のワークショップ
チームビルディングの現場では、競争と協力の両方の要素を含むワークショップが効果を発揮しています。例えば「タワービルディング」というアクティビティでは、複数のチームに分かれて制限時間内に高いタワーを作るという競争をしながらも、チーム内では協力が必須となります。
ソニー株式会社の新入社員研修では、このようなハイブリッド型のチームビルディングを導入した結果、参加者の87%が「競争と協力の両方の重要性を理解できた」と回答しています。
別の例としては「脱出ゲーム」形式のワークショップも人気です。各チームが部屋から脱出するために競い合いながらも、チーム内では多様な視点からの協力が求められます。こうした体験を通じて、メンバーは「健全な競争」と「効果的な協力」の両方を体感できるのです。

あなたのチームでも、こうしたワークショップを取り入れてみませんか? 普段の業務では見えない一面を発見できるかもしれません。
日常業務に取り入れられる工夫
ワークショップだけでなく、日常業務の中でも競争と協力のバランスを取る工夫ができます。以下に具体的な取り組みをまとめました:
| 取り組み | 競争の要素 | 協力の要素 |
|---|---|---|
| チーム対抗KPI | チーム間で成果を競う | チーム内で協力して目標達成 |
| ピアボーナス制度 | 評価される意欲が競争心に | 互いの貢献を認め合う文化醸成 |
| 定期振り返りミーティング | 個人の成長目標を共有 | 互いにアドバイスし合う |
| ローテーション制 | 様々な役割での能力発揮 | 異なる視点の理解と協力 |
トヨタ自動車では「小集団活動」と呼ばれる取り組みで、チーム対抗で業務改善を競いながらも、チーム内では協力してアイデアを出し合い、全社的にはその成果を共有する文化を育んでいます。
また、Salesforceでは四半期ごとの「V2MOM(Vision, Values, Methods, Obstacles, Measures)」という目標設定と振り返りのフレームワークを使い、個人とチームの両方の成果をバランスよく評価しています。
あなたの組織では、どのような取り組みが可能でしょうか? 既存の制度や文化の中で少しずつ変化を起こしていくのがおすすめです。
リーダーとして意識すべきポイント
チームのバランスを取るには、リーダーの役割が非常に重要です。リーダーとして何を意識すべきか、具体的に見ていきましょう。
チームメンバーの個性を活かす関わり方

チームには競争を好むメンバーと協力を重視するメンバーが混在しています。それぞれの特徴は以下のように見分けることができます:
競争を好むタイプ
- 個人の目標や成果を頻繁に話題にする
- 自分の貢献を積極的にアピールする
- 明確なフィードバックや評価を求める
- 結果にこだわる傾向がある
協力を好むタイプ
- チームの雰囲気や人間関係を大切にする
- 他者のサポートや調整役を担うことが多い
- プロセスや学びを重視する
- 共同作業に充実感を感じる
リーダーはこうした個性を理解した上で、競争派には個人の成長機会と成果の可視化を、協力派にはチームへの貢献の価値を認める接し方をすることで、それぞれの強みを引き出せます。
例えば、ある製造業のマネージャーは、競争好きな社員には個人の技術向上コンテストを設け、協力重視の社員にはメンター制度の中心を担ってもらうことで、チーム全体のバランスを取ることに成功しています。皆さんのチームでも、メンバーの個性に合わせた役割分担を考えてみてはいかがでしょうか?
問題が起きたときの対処法

競争と協力のバランスが崩れると、チームに様々な問題が発生します。早期発見のためには、以下のサインに注意しましょう:
- チーム内での情報共有が減少している
- ミーティングでの発言が特定のメンバーに限られる
- 成功を喜び合う文化が薄れている
- 失敗を隠す傾向がある
- 「私の仕事」「あなたの仕事」という境界が厳格になる
こうした状況を改善するためには、具体的な対話が効果的です。例えば:
「最近、情報共有が少なくなっていると感じています。みんなが持っている知識や経験を共有することで、チーム全体がもっと成長できると思うのですが、どうすれば共有しやすくなるでしょうか?」
このような問いかけから始めることで、メンバー自身が問題を認識し、解決策を考えるきっかけになります。IT企業のある部門では、過度な競争によってチームの分断が起きた際、「自分の成功体験」ではなく「自分の失敗と学び」を共有するセッションを行ったところ、徐々に協力的な雰囲気が戻ってきたという事例もあります。
皆さんのチームで問題が起きたとき、まずは何が起きているのかを客観的に観察し、オープンな対話を心がけてみましょう。
長期的な視点でのチーム育成
競争と協力のバランスは、チームの成熟度によっても変化します。以下の段階に応じたアプローチが効果的です:
- 形成期:まずは協力の基盤を固める時期。信頼関係構築を優先し、競争は控えめに
- 混乱期:適度な競争を導入し、個々の役割や責任を明確化
- 統一期:チーム間競争を取り入れ、チーム内の結束を強化
- 機能期:個人とチームの両方の成果を評価する複合的な仕組みを導入
評価制度も重要な要素です。短期的な数値だけでなく、チームへの貢献度や他メンバーの成長支援なども評価指標に含めることで、バランスの取れたチームづくりを促進できます。アクセンチュアでは「Performance Achievement」という評価制度を導入し、個人の成果だけでなく、チームへの貢献やメンバーの育成も重視する仕組みに変更。その結果、従業員満足度が16%向上したと報告されています。
皆さんの組織の評価制度は、競争と協力のどちらに偏っていますか? 長期的な視点で見直す余地はありませんか?
ピックアップ記事

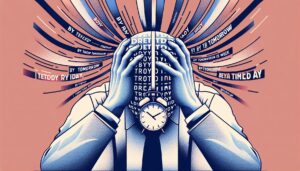



コメント